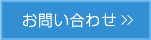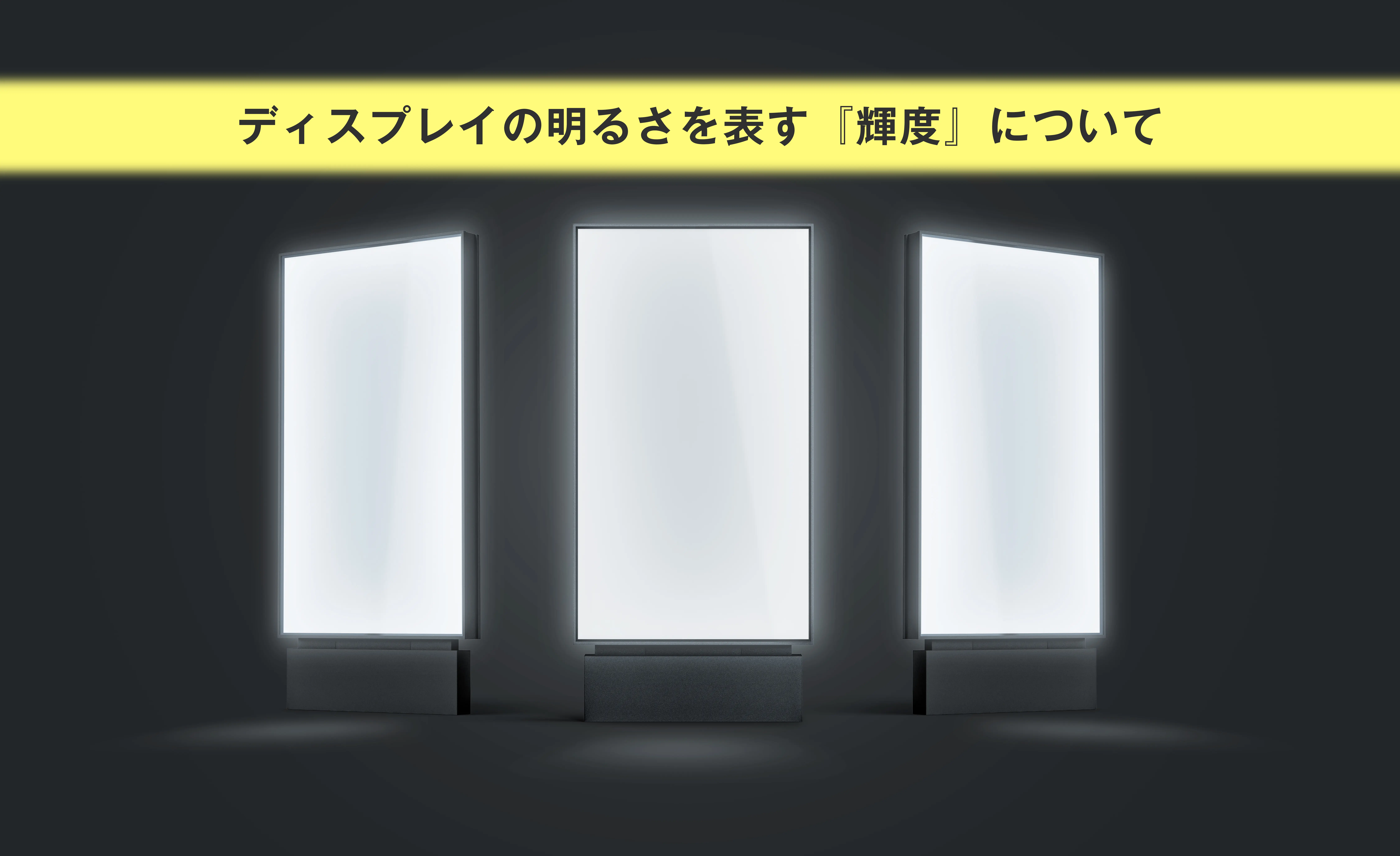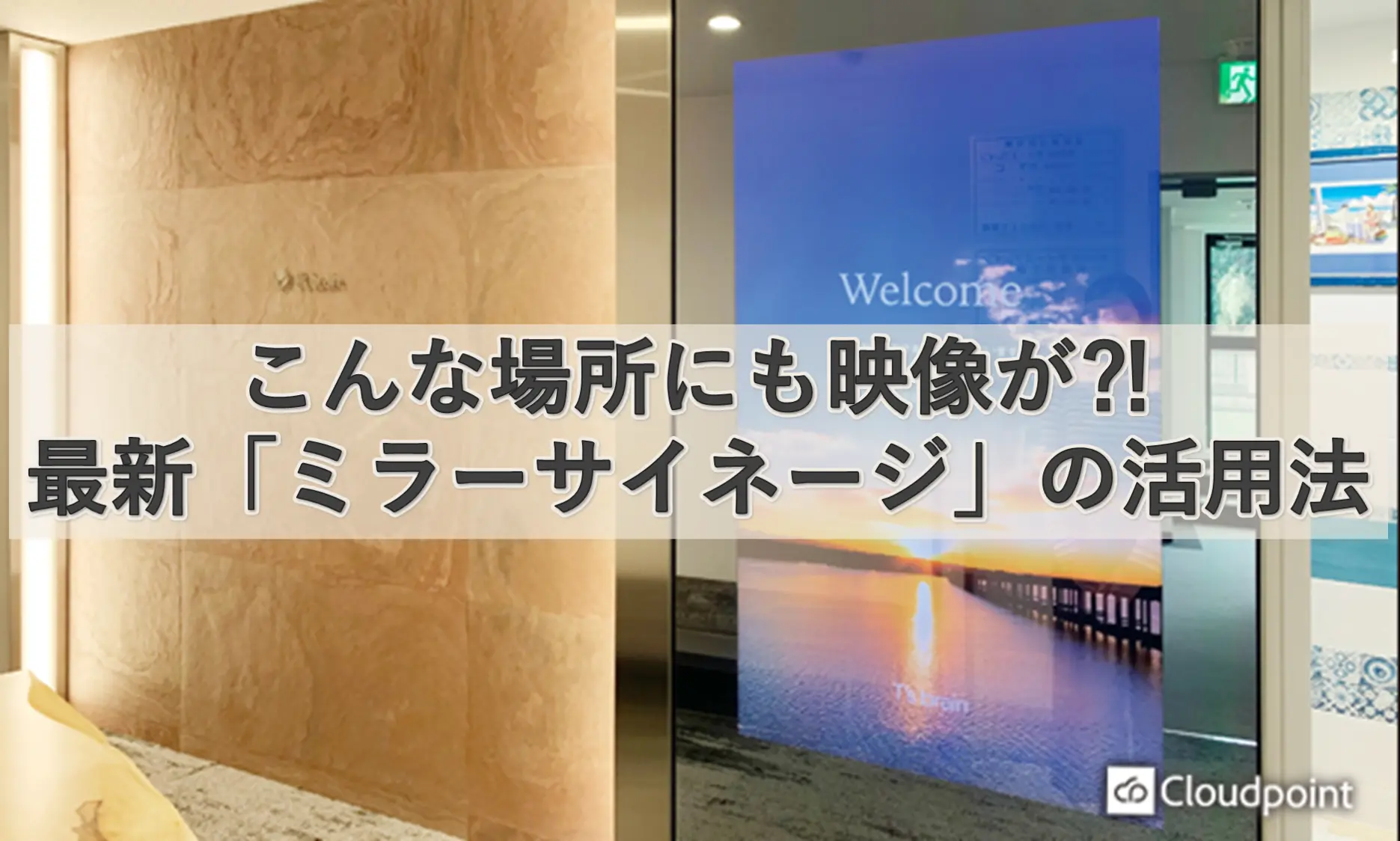事例
Case【初心者向け】街頭の大型サイネージ
2017.04
大型サイネージ導入時の、見られ方の検討ポイント。
■限られた広告エリアを有効活用
デジタルサイネージはひとつのディスプレイでも見せ方を増やしていくことで、付加価値をあげることができます。
例えば、広告ポスターをデジタル化し店頭に置くだけではなく、映像が流れていないときには透過するLCDディスプレイを店頭に置き、商品紹介の映像を流し、その後に実際の商品がパッと現れるような仕掛けを作るようなことが考えられます。
また、当社製品の調光フィルムTANYOを大きなガラス面に施工し、昼間はガラス面として店内を見せ、夜は乳白色に切りかえ、プロジェクタ―でガラス面全面をディスプレイとして使い、外に向けたプロモーション映像を流すといった演出をすることもできます。
また建物の有効活用という観点から、広告媒体、集客目的、エンターテインメント性を持たせた演出の一部として、大型のデジタルサイネージを導入するケースが増えてきています。
■マルチディスプレイ
よく店舗屋外などで見る数台のディスプレイを連結させ、一つの大きなディスプレイとして使っているものがありますが、あれは「マルチディスプレイ」と呼ばれています。
一枚の大きなディスプレイは受注生産のものがほとんどで価格が非常に高いのに比べ、マルチディスプレイにすると大量生産されている安価なサイズのディスプレイを利用できるので予算が抑えされます。
大型サイネージとしてメリットの多いマルチディスプレイですが、狭額ベゼルを用いてもどうしても境い目ができるので、コンテンツはマルチ用に作成する必要があり文字が入る場合などは特に配慮が必要です。
また、設置をする上で注意をしなければならない点は景観条例です。
エリアごとに厳しいルールが設けられている地域もありますし、そういったルールがない場所でも近隣の方々を考え自動輝度調整の機能を備えたものなどを選定されることをお勧めします。
■空間演出としての大型サイネージ
20年ほど前までは、大きな映像といえば映画館ぐらいでしかみられませんでしたが(恐らく)、最近では当社製品VEGAS VISIONシリーズのようなLEDビジョンや、マルチディスプレイの普及が進み、街なかでもよくみかけるようになりました。
しかも、遠くにある大きなスクリーンを「眺める」のではなく、間近で自分の体より大きな映像を「感じる」インパクトはとても大きいものがあり、広告媒体としても、空間演出効果としても、とても有効です。
■インタラクティブに
広告媒体としては、インテラクティブな機能を持つ大型サイネージの事例が、新宿駅前東口のアインズアンドトルペさんの薬局の店舗ガラス面にあります。

https://www.cloudpoint.co.jp/blog/2016/05/23/post-160523/
こちらは60インチ縦3×横8面で構成されたマルチディスプレイが設置されており、カメラが6台付いています。
このカメラと連動させ、前を通る人に拡張現実(AR)を見せ、注目してもらおうというコンテンツを流しています。
ディスプレイの前を通ると、ディスプレイに映ったモデルさんが目で追いかけてきたり、顔認識技術で通行人にリアルタイムに面白い帽子などをかぶせたりといった、インタラクティブな表現で効果的に顧客誘引ができます。
こういった参加型のコンテンツは、注目を集められるだけではなくインパクトを与えやすいので、体験した人の記憶に強く残り、とても効果的ではないかと思います。
■アートのように
渋谷のクオーツタワー館内入口にあるデジタルサイネージでは美術館の絵画展示のように、縦や横にディスプレイを設置して海底のイメージ動画などを放映しております。(写真左)


それとは別に情報発信用の2×4面構成のマルチディスプレイが隣の壁面に設置されています。
サインとしてのディスプレイと、アート演出としてのディスプレイを併用している面白い事例です。
(写真右)
このほかラッピングされた柱に設置され、そのラッピングシートの図版と一体化するよう調整された映像を流したり、四面柱の周りにディスプレイを取り付け、あたかもその柱がウィンドウディスプレイのようになっているように見せたり、中で商品が浮いているように見せる、アート作品のようなデジタルサイネージもたくさんあります。
クラウドポイントは、デジタルサイネージとスペースデザインを融合させ、情報発信にとどまらない、街を歩く人をワクワクさせるような空間演出も行ってまいります。
最新記事
カテゴリ別
月別アーカイブ
- 2024年8月 (6)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (5)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (3)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (4)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (5)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (5)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (1)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (2)
- 2018年8月 (5)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (3)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (3)
- 2017年2月 (6)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (2)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (11)
- 2016年9月 (14)
- 2016年5月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (2)
- 2014年12月 (2)
- 2014年11月 (3)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (2)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (2)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (2)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (2)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (3)