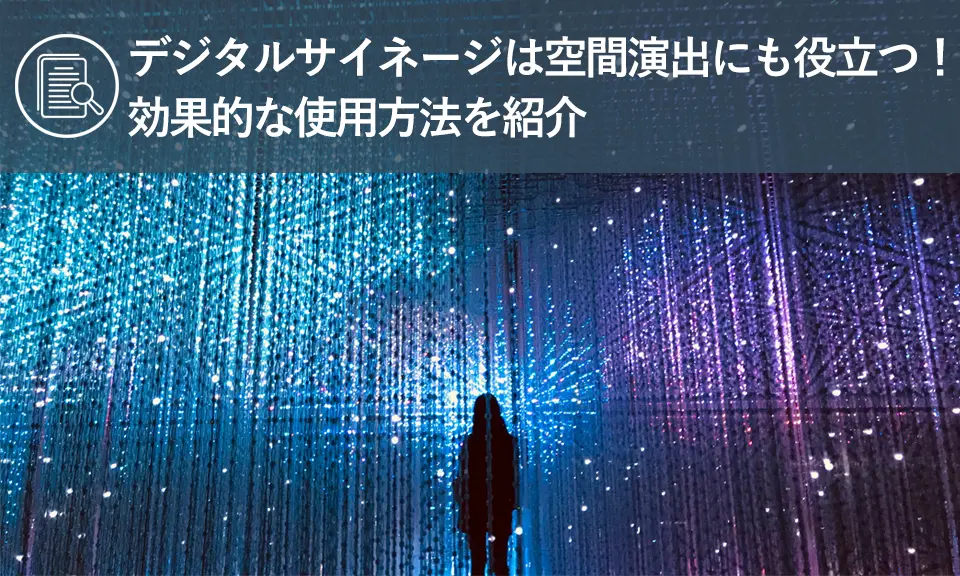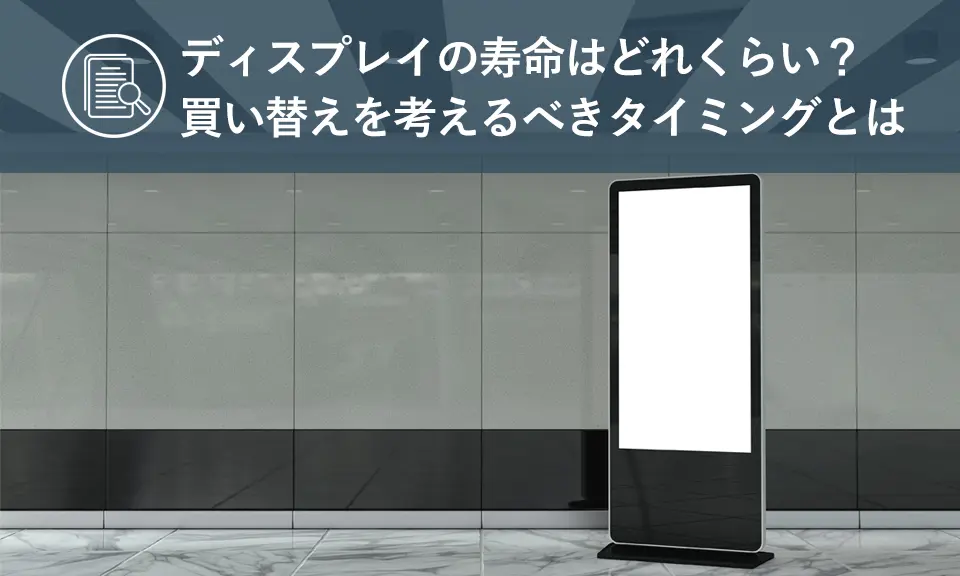コラム
Column調光フィルムの寿命はどれくらい?長く使うためのポイントを押さえよう
2025.03
![]()
調光フィルムは手間なくプライバシーを保護できて便利ですが、どのくらいで寿命を迎えるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、調光フィルムの寿命を解説します。長く使用するためのポイントやメリットも紹介しますので、
調光フィルムの導入をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
調光フィルムとは
まずは、調光フィルムについて説明します。
調光フィルムとは?
調光フィルムとは、スイッチの切り替えでガラスの透明度を調節できるフィルムのことを指します。
PLDC方式のものが一般的で、フィルム内部の液晶分子に電流を流すことで透明・不透明を瞬時に切り替える仕組みです。
調光ガラスの改良や競合が進んで市場価格が下がったことで、商業施設や住宅などの建物への需要が拡大し、
オフィスや事務所、店舗などさまざまな場所で活用されています。
![]()
調光フィルムの制御方法
<スイッチ式>
スイッチ式の調光フィルムは、照明のようにスイッチで簡単に透明度を調節できます。
コントローラーやリモコンを併用すれば遠隔操作が可能な場合もあるので、設置する環境に合わせてフィルムの種類や制御方法を選択するとよいでしょう。
<センサー式>
センサー式の調光フィルムは、特定の条件に合わせて自動的に透明度を調節します。
直射日光に反応するセンサーを利用すれば、商品の劣化や退色の予防が可能です。
また、センサー式の調光フィルムはリモコン操作の手間がかからないので、自動的に透明度を調節してもらいたい場合にも適しています。
調光フィルムの活用シーン
<会議室や応接室のガラスパーテーションとして>
調光フィルムを会議室や応接室のガラスパーテーションに活用すると、柔軟なプライバシー管理が可能になります。
透明な状態で使用すれば開放的な雰囲気を演出でき、スタッフ同士のコミュニケーションが生まれやすくなる点もメリットといえるでしょう。
<事務所や店舗の夜間広告として>
道路に面した窓に調光フィルムを貼れば、夜間に広告スクリーンとしての活用も可能です。
<映像投影場所として>
調光フィルムは、不透明に調節すれば映像投影場所としても活用できます。
会議資料やプロジェクションマッピングの投影に適しており、狭い空間でも使用しやすく、高いコントラスト比で映像が見やすい点もメリットです。
![]()
調光フィルムの寿命
ここからは、調光フィルムの寿命を解説します。
調光フィルムの寿命
調光フィルムの寿命は設置環境によって様々ですが、紫外線が当たる場所や結露が生じやすい場所では劣化が早まる可能性があります。各メーカーの一般的な保証期間は約1年のものが多く、保証期間終了後は修理や交換に費用がかかるため、調光フィルムの寿命を延ばすための対策を考えることが大切です。
調光フィルムの寿命を延ばす方法
<定期的なメンテナンスと清掃>
定期的なメンテナンスや清掃を心がけると、調光フィルムの寿命を延ばす効果が期待できます。
湿った柔らかい布で表面を拭き取ればホコリや汚れを取り除けるので、こまめな清掃に負担を感じにくい点もメリットです。
![]()
<使用中に頻繁に電源を切り替えない>
調光フィルムの使用中は、頻繁に電源を切り替えないようにしてください。万が一故障した場合は、専門業者への修理依頼が必要です。
<頻繁な交換や移動を避ける>
調光フィルムを活用する際は、頻繁な交換や移動は避けましょう。調光フィルムを頻繁に交換すると、ガラスを傷つけるだけでなく、配線ルートに影響を及ぼす可能性もあります。
<シーリングの状態をこまめに確認する>
調光フィルムを設置する場合は、シーリングの状態をこまめに確認しましょう。シーリングが劣化すると、調光フィルムの性能が損なわれる可能性があるため、再度シーリングを施工する必要があります。
調光フィルムの強み
ここからは、調光フィルムの強みを紹介します。
手間なくプライバシーの確保ができる
調光フィルムは、一般的なガラスに調光フィルムを貼りつけるだけで、手間なくプライバシーを確保できます。
スイッチで外からの視線を瞬時に遮られるので、急な来客にも柔軟な対応が可能です。
また、調光フィルムを活用すると個人情報や機密情報のプライバシー管理がしやすくなり、会議や診察に集中できるメリットもあります。
プロジェクターにも使える
調光フィルムを不透明な状態にすると、プロジェクターとしても使用できます。
調光フィルムをつなぎ合わせれば大画面での演出も可能で、モニターでは実現できない迫力のある映像を高画質で楽しめます。
室内環境を快適にする
調光フィルムは通常のガラスよりも直射日光を遮る性質や保温性があるので、室内環境を快適にする効果が期待できます。
夏場は室温が上昇しやすく、窓際は部屋の温度が8~12℃上がる場合もあるので、調光フィルムで室内に入る直射日光を遮ることが大切です。
また、冬場は暖かい空気が窓から逃げやすくなりますが、調光フィルムの保温性を活用することで光熱費も節約できます。
場所の広さに関係なく導入しやすい
調光フィルムは、場所の広さに関係なく導入しやすい傾向があります。
加工の自由度が高く、大きさや形状を問わず数ミリ単位で調節できる点もメリットです。
また、調光フィルムは粘着力が高く、壁やカーテンよりも空間を多目的に使用できる上に、部分的な加工やドア部分への貼りつけも可能です。
デザイン性の高い調光フィルムを導入すれば、企業イメージの向上効果も期待できるでしょう。
空間の用途に合わせて柔軟に対応できる
調光フィルムを導入すると、空間の用途に合わせた柔軟な対応が可能です。
スイッチを押してから瞬時にガラスの透明度を調節できるので、急な来客や会議の際も素早く切り替えられます。
また、調光フィルムは開放的な空間をつくりたい場合は透明に、プライバシーを確保したい場合は不透明に変化させるなど、
デザイン性と機能性を両立できる点も魅力の一つです。
おしゃれさを損なわない
調光フィルムは、カーテンやブラインドのように空間を圧迫することが少なく、おしゃれさを損ないません。
見た目がスタイリッシュでほかのインテリアとの調和を乱さないので、オフィスなどで空間をおしゃれに演出したい場合にもおすすめです。
調光フィルムでおしゃれな空間を演出することで、職場の満足度が上がり会社の生産性向上につながる可能性もあります。
まとめ
調光フィルムの寿命を延ばすためには、メンテナンスや清掃を定期的に行い、
故障につながる使用方法を避けることが大切です。
調光フィルムは加工の自由度が高く、瞬時に透明・不透明を切り替えられるので、プライバシー管理やセキュリティ対策を目的とした導入もおすすめです。
条件が合う場合は、電源でON/OFFが可能な調光フィルム「TANYOFOGLEAR」をお使いください。
最新記事
カテゴリ別
月別アーカイブ
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (3)
- 2025年2月 (3)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (6)
- 2024年10月 (1)
- 2024年8月 (6)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (5)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (3)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (4)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (5)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (5)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (1)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (2)
- 2018年8月 (5)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (3)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (3)
- 2017年2月 (6)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (2)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (11)
- 2016年9月 (14)
- 2016年5月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (2)
- 2014年12月 (2)
- 2014年11月 (3)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (2)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (2)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (2)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (2)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (3)