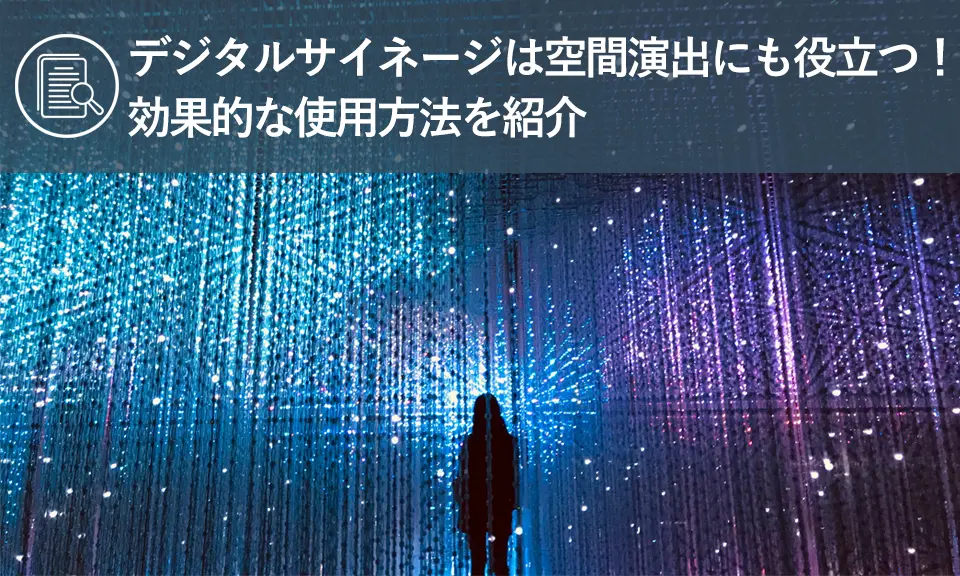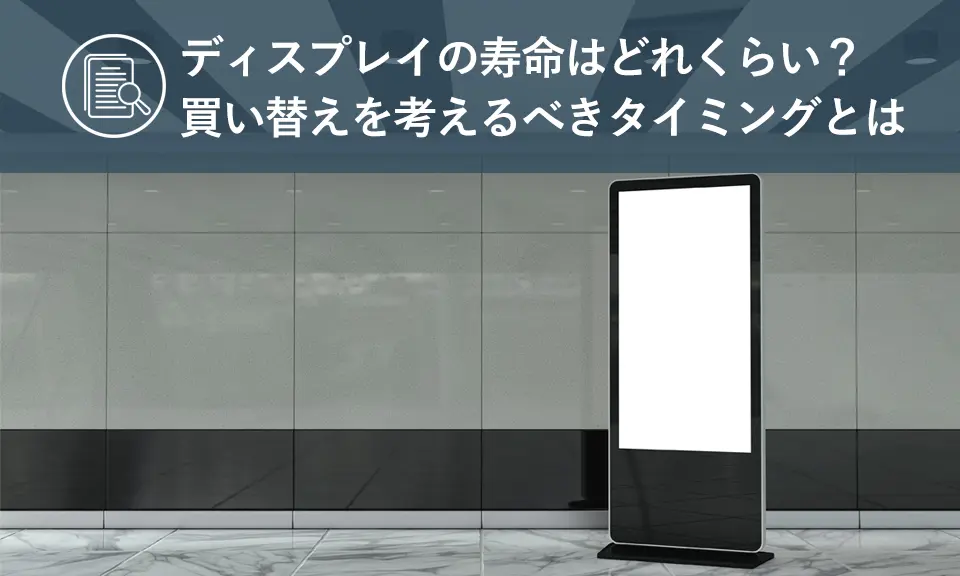コラム
Columnディスプレイの寿命はどれくらい?買い替えを考えるべきタイミングとは
2025.02
- Category
- デジタルサイネージ
![]()
ディスプレイは、日常生活や仕事に欠かせないアイテムです。
しかし、どんな製品にも寿命があり、適切なタイミングでの買い替えが必要です。使い続けることで生じるトラブルや
劣化のサインに気づくことが、快適に使用するポイントになります。
本記事では、ディスプレイの寿命に関する基礎知識と、買い替えのタイミングについて解説します。
また、長く使用するための工夫もお伝えしているので、ぜひ参考にしてください。
ディスプレイの寿命
ここでは、ディスプレイの寿命や処分方法、寿命を縮める原因について解説します。
寿命には2種類ある
<法定耐用年数>
法定耐用年数とは、製品を資産として捉えた場合に、減価償却を行う期間を示すものです。用途によって法定耐用年数は異なり、例えばデスクトップパソコンのモニターとしてディスプレイを使用する場合は「その他事務機器」に分類され、耐用年数は5年とされています。
一方、デジタルサイネージとして利用する場合は「器具備品」に該当し、耐用年数は3年です。
<製品としての耐用年数>
製品としての耐用年数とは、一般的な使用環境下で、どのくらいの期間正常に機能するかを示す目安です。
この期間を過ぎると、不具合や故障が発生するリスクが高まり、買い替えを検討するタイミングとなります。
業務用ディスプレイの場合、一般的な耐用年数はおよそ4~5年とされていますが、設置環境や使用頻度、メンテナンス状況などによって実際の寿命は大きく変わるのが普通です。
ディスプレイの寿命
ディスプレイの寿命(輝度半減期)は、一般的に15,000~50,000時間とされ、1日12時間使用する場合は、
約4~6年程度が目安です。一方、1日8時間の使用では5~10年ほど使用可能とされていますが、前述のとおり寿命は使用環境や使用頻度によって大きく変わります。
長期間使用することで経年劣化が進むと、画質の低下や動作不良が見られることもあるでしょう。
寿命の目安が記載されているモデルもあるため、購入時に確認することで買い替え時期の参考になります。
※輝度半減期とは…輝度半減期とは、光源の輝度が初期値の半分にまで低下するまでの時間を指します。
ディスプレイの処分方法
家庭で使われるディスプレイは、リサイクル法の対象品目であり、通常のごみ回収に出せないため、自治体のルールに従い適切に処理しなければなりません。
一般的には、メーカーの回収サービスや自治体が設置する回収ボックスを利用する方法があります。
リサイクルマークが付いている製品は無料で引き取られる場合もありますが、ない場合は回収費用が必要です。
また、まだ使用可能なディスプレイの場合は、リサイクルショップでの買取や下取りに出すことで再利用につながることもあります。
ディスプレイの寿命を縮める原因
電源をつけっぱなしにしていると、内部の部品に負担がかかり、経年劣化を早める要因となります。
また、高温多湿の環境や直射日光が当たる場所での使用も、熱による部品の劣化や液晶の変色を引き起こし、
寿命を短くする原因です。
さらに、頻繁な電源のオン・オフも、部品に負荷をかけるため注意しましょう。
寿命と決めつける前に確認しておきたいこと
ディスプレイが寿命かどうかを判断する前に、以下の確認を行いましょう。
- ●電源の確認:パソコンやディスプレイの電源を一度切り、再度入れ直して動作を確認する。
- ●接続ケーブルの確認:ディスプレイとパソコンの接続ケーブルが正しく挿し込まれているか、緩みや断線がないかをチェックする。
- ●デバイスドライバーの更新:パソコンのディスプレイドライバーが最新の状態になっているか確認する。
- ●別のパソコンでの動作確認:ほかのパソコンにディスプレイを接続し、正常に動作するか試す。
- ●電源ケーブルの確認:ディスプレイ本体の電源ケーブルを抜き差しして、正しく接続されているかを再確認する。
このように、何が原因で不具合が発生しているのか確認することで、故障や寿命以外の問題にも対処しやすくなります。
ディスプレイの買い替えを考えるべきタイミング
ここからは、ディスプレイの買い替えを考えるタイミングを紹介します。
画面が暗い・色が以前よりも薄い
ディスプレイの画面が暗くなったり、以前より色が薄く感じられたりする場合は、バックライトの劣化によることが多く、寿命が近づいているサインです。
特に、画面全体が白っぽく見えたり色にムラが生じたりする場合は注意しましょう。
ただし、設定が意図せず変更されているケースもあるため、彩度や輝度などのディスプレイ設定を一度確認してみることも大切です。
画面のちらつきがある
画面のちらつきは、液晶パーツやバックライトの劣化が主な原因であり、寿命が近づいている兆候と考えられます。
ただし、パソコンとディスプレイを接続するケーブルの接触不良や、機器の帯電が原因の場合もあるため、すぐに寿命と判断はできません。ケーブルを挿し直す、接続環境を整える、放電を試みるなどの対策を行っても改善されない場合は、買い替えのタイミングといえるでしょう。
画面に線がある
ディスプレイの画面に線が現れる場合、液晶パネルの劣化が原因であることが多く、放置すると画面全体が正常に表示されなくなる可能性があり、買い替えのタイミングです。
線は、黒やカラフルな色で表示され、時間の経過とともに増えたり太くなったりすることもあります。
ただし、接続しているケーブルやパソコン本体のグラフィックボードに問題がある場合もあるため、まずは別のディスプレイに接続して確認してみましょう。
![]()
画面が赤い
画面が赤みを帯びる症状は、バックライトの劣化が主な原因です。
ディスプレイに使われているバックライトにはCCFL(冷陰極蛍光管)やLEDなどがあり、これらが老朽化すると色のバランスが崩れ、正常な表示が困難になります。
ただし、ディスプレイの設定によって赤色が強調されている可能性もあるため、まずは画面の色調整や設定を確認しましょう。
設定を見直しても改善されない場合は、バックライトの寿命が近いサインといえます。
映らない
画面が映らない場合は、まず電源や接続の状況を確認しましょう。電源ケーブルが抜けている、接続ケーブルが緩んでいる、または画面オフ機能が作動しているなどの要因が考えられます。
それでも改善されない場合は、ディスプレイ自体が寿命を迎えている可能性が高いでしょう。
特に、電源が入っていても何も映らない場合は、内部の故障が原因であるケースが多く、買い替えを検討するタイミングになります。
もっと作業効率を上げたい
作業効率を向上させたいと感じたときも、ディスプレイの買い替えを検討するよいタイミングです。
現在のモニターに問題がなくても、最新のモデルに替えることで、画面の見やすさや表示性能が大幅に向上し、業務の快適性が高まる可能性があります。
特に、モニターサイズを大きくしたり高解像度のモデルを選んだりすることで、作業領域が広がり、複数のウィンドウを同時に扱う作業もスムーズになるでしょう。
また、モニターを追加すれば、一度に多くの情報を確認しながら効率的な作業ができるようになります。
耐用年数が近い
耐用年数が近づいているディスプレイも、買い替えを検討しましょう。使用に問題がない場合でも、最新の製品と比較すると画質や省電力性、機能面で差が生じることがあります。
特に、より効率的な作業や快適な使用環境を求める場合は、新しいモデルへの切り替えが効果的です。
ただし、耐用年数はあくまで目安であり、状態によっては継続使用が可能なケースもあるため、自分のニーズや目的に合わせて最適な判断をしましょう。
ディスプレイの寿命を延ばすためのポイント
ディスプレイの寿命を延ばすには、日常の使い方や工夫が大切です。
最後に、適切なケアで長く快適に使用する方法を紹介します。
使わないときは電源を切る
長時間電源が入ったままの状態は、内部の部品に負荷をかけ、ディスプレイの寿命を縮める要因となります。
ディスプレイを使わないときは、電源を切りましょう。
ただし、頻繁に電源をオン・オフする行為は、逆効果になる場合があるため注意しましょう。
短時間の離席や一時的に使用を中断する際は、スリープモードを活用すると負担を軽減できます。
室温を一定に保つ
極端な高温や低温の環境も、内部の部品に負担をかけるため、ディスプレイの劣化を早める原因です。
また、急激な温度変化による結露は、液晶パネルや内部回路にダメージを与える可能性があります。
特に寒冷地や暑い地域では、エアコンや加湿器を利用して快適な温度と湿度を保つことが大切です。
画面の明るさを調整する
過度に明るい設定では、バックライトに過剰な負担がかかり、結果として寿命が短くなってしまう可能性があります。
一方で、暗すぎる設定も目に負担をかけるため、適切なバランスが必要です。
使用環境の明るさに応じて画面の輝度を調整し、必要以上に明るさを上げないよう心がけることで、ディスプレイの寿命を延ばせます。
また、エコモードを活用するのも効果的です。
ディスプレイを掃除する
ディスプレイの寿命を延ばすには、定期的な掃除が大切です。通気口にホコリがたまると、熱がこもりやすくなり、機器内部の温度が上昇して寿命を縮める原因になります。
掃除の際は、液晶画面を強く押さえたり、水分が入り込んだりするような方法は避けてください。
クリーニングクロスやOA機器用のハタキを使って、丁寧に汚れを取り除くことが大切です。また、静電気によるダメージを防ぐため、掃除前には必ず電源を切りましょう。
![]()
まとめ
ディスプレイの寿命や買い替え時期を正しく理解し、適切な対応を行うことで、快適で効率的な作業環境を保てます。
また、使用方法の工夫やこまめな掃除など、日常的なケアが寿命を延ばすポイントになります。
適切な管理でディスプレイを最大限活用しつつ、性能の低下を感じた際は新しいモデルへの買い替えも検討することで、
よりよい作業環境を手に入れましょう。
最新記事
カテゴリ別
月別アーカイブ
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (3)
- 2025年2月 (3)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (6)
- 2024年10月 (1)
- 2024年8月 (6)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (5)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (3)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (4)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (5)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (5)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (1)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (2)
- 2018年8月 (5)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (3)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (3)
- 2017年2月 (6)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (2)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (11)
- 2016年9月 (14)
- 2016年5月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (2)
- 2014年12月 (2)
- 2014年11月 (3)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (2)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (2)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (2)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (2)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (3)